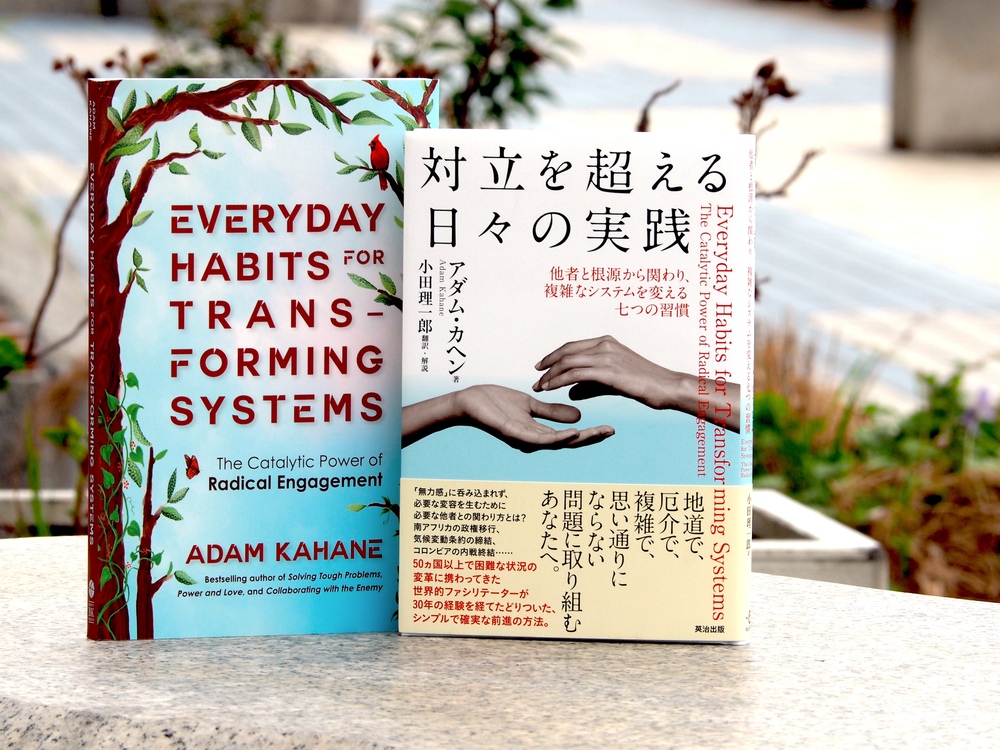News & Columns
アダム・カヘンの6冊目となる新著『Everyday Habits for Transforming Systems』が2025年4月に発刊され、日本語翻訳本『対立を超える日々の実践──他者と根源から関わり、複雑なシステムを変える七つの習慣』も同年9月に英治出版より発刊されました。この新刊のテーマは、システムチェンジを創り出すチェンジメーカー、チェンジ・エージェントとも言われる「システムリーダーたち」の日々の習慣についてです。翻訳、解説はチェンジ・エージェント社代表の小田理一郎が担当させていただきました。
本書の「訳者解説」を出版社からの許可を得て掲載します。
システム変容と、愛と力、正義について(翻訳者解説)
現在の世界的な潮流のなかで、この70~80年間国際社会が指向してきた価値観は大きく揺らいでいます。自国第一主義の資源やテクノロジーをめぐる争奪戦、広がるポピュリズムと権威主義、さらに格差の拡大と、人道的危機、気候危機や生物多様性といった複合的な危機が深刻さを増し、私たちに迫っています。
こうした体制レベルおよびその地盤レベルでの変化に伴う厄介な問題は、直線的な因果関係では説明できないことです。また、誰か一人のトップ、一つの組織が解くこともかないません。にもかかわらず、私たちはこのような課題に対して、「力の行使」に訴えるか、そうでなければ「無力感」にとらわれるかになりがちです。その結果同じ轍を回り続けるか、変化しても退行的な方向に向かってしまう傾向があります。
本書は、こうした世界的な潮流のなかにあっても、対話と協働のアプローチをもってこの行き詰まりを打破し、うまく機能していないシステムを変容することは可能であること、またそのカギがシステム変容を欲する私たち一人ひとりの日々の実践にあることを提示します。
著者アダム・カヘンは、南アフリカの民主化プロセスからコロンビアの和平交渉、生産者から消費者まで巻きこむ食糧システムの改革、気候変動対策の国際協働に至るまで、30年以上にわたり、世界50カ国で分断された当事者たちが未来を共につくる協働の場とプロセスを支援してきました。彼と共に働いた多くの人々は、互いの違いを越えて粘り強く協働し、前進を積み重ねながら、システム変容を実現していきました。
システム変容と本書の意義
「システム変容(systems transformation)」とは、問題が起きてから対処、適応するのではなく、問題の発生する根本原因を取り除くべく、そのシステムの根底にある構造や価値観そのものを変えていく営みやプロセスです。社会課題などにおいて、栄養不良やホームレスなど、問題の影響が及んだ人たちへ「炊き出し」「シェルター提供」などの支援・人道サービスを提供するのではなく、あるいは、起きていることに事後的に適応するのでもなく、そもそも問題が発生する根本原因への働きかけであるのが特徴です(日本では「システムチェンジ」という表現が広がっていますが、本書では著者が一貫して使ってきた表現である「システム変容」を訳語として採用しています)。
もとより、組織や事業の課題であれ、社会や経済の課題であれ、今のパフォーマンスを出すべく設計されているシステムそのものの変容は容易なことではありません。より多くの当事者や目的が混在する社会的に複雑なシステムの変容は、組織のリーダーや専門家が行う「計画、組織化、コントロール」といった従来型のマネジメントやトップダウンのアプローチだけでは成し遂げられず、むしろ「システムによる抵抗」に直面することが多くの政策や戦略で確認されています。
システムの挙動を理解するには、「氷山モデル(出来事、挙動、構造、メンタルモデル)」の例えにあるように、海面下にあって見えにくい全体像、とりわけ「アーティファクト(人間の営みでつくられた構造とその痕跡......政策、評価基準、組織構造、インフラ、利用される技術、規制など)」と「メンタルモデル(意識・無意識にもつ前提......価値観、想定、習慣的な行動様式など)」の間で起こる相互作用の理解が欠かせません。この相互作用の堅固さにより一見変わらないように見えるシステムであっても、変わりうると認識することが大切です。ただしシステムを変えるには、それを変えうると考える当事者たちが共に望むシステムの全体像を共有し、「裂け目」とも呼ばれる突破口を探しだし、十分多くの人たちが介入できる場所に働きかけることが求められます。
本書で書かれているような数々のブレイクスルーや「生成的」なシステム変容の事例は、しばしばボトムアップに、互いの関係を築き、対話し、協働する過程を通じて実現しました。本書はそうした事例に登場する、世界で注目される社会システムの変容に関わった主体者、当事者たちに焦点を当てて数多くのインタビューを実施し、システム変容を意図的に起こすために必要なことは何かを探求するものです。
根源からの関わり(ラディカル・エンゲージメント)がシステム変容の触媒となる
そして、著者アダムが見出したのは、そのシステムの内外で関わる人たちによる「根源からの関わり(radical engagement)」が、システム変容のカギとなることです。「エンゲージメント」という言葉は、ステークホルダー間や会社と社員の関係などの文脈で近年注目されており、強制や諦め、関係の断絶ではなく、他者に向き合い続けながら、傾聴、対話、協働などを通じて関わり続ける姿勢を意味します。日本人も「粘り強いエンゲージメント」において国際的に評価を得ています。
アダムの「ラディカル・エンゲージメント」は、さらに一歩踏みこみます。ここでいうラディカルとは一般的にイメージされる「過激」という意味ではなく、本来の語源である「根源」という意味です。システムを根本から変容するには、私たちが根源に立ち返り、他者とより深いレベルでつながることが求められます。この関係の質の変化が、システム変容の触媒となり、生成的、連鎖的で持続的な変化を可能とします。
そしてこの根源からの関わりは、特別なとき、特別な人だけに限って発揮されるものではありません。自分自身の日々の行動習慣として定着し、あり方として体現されることで真価を発揮します。本書で紹介される七つの習慣を実践するのに、特別な地位や権限は必要ありません。簡単なものではなく、自分の枠組みを広げるチャレンジングな試みではありますが、意識すれば誰でも職場や地域、家族で今日から実践できます。そして、小さな実践と枠組みを広げるストレッチの積み重ねが、やがてより大きなシステムに影響を与えます。
日々の実践がもたらすもの
私たちは、日々意識せずにいつもの思考、会話、行動の習慣をくり返します。しかしそれが目的の達成や成長に結びつくとはかぎりません。振り返りを怠れば、惰性で低きに流れることもあります。だからこそ私たちは、習慣を意識的に見直すことが大切です。アダムの提示する七つの習慣は、惰性的な習慣を打破するための新たな習慣とも言えるでしょう。
ジャーナリストであり、社会改革に多大な貢献をしたジェイコブ・リースは、次のような格言を残しています。「何も手立てがないように思えるとき、私は石工が岩を叩き続けるのを見に行く。100回叩いてもひび一つ入らない。しかし101回目の一撃で岩は二つに割れる。そして私は、それが最後の一撃ではなく、それまでのすべての打撃がそうさせたのだと知る。」
意識的なストレッチを日々の習慣にとりこむことで、自身の可動域を広げることが可能になります。可動域が広がり、無意識にできることが増えていけば、かつて無理だと思ったこともできるようになっていきます。それと同様に、「根源」へ立ち返る習慣は、どれも容易ではありませんが、日々のくり返しを通じてよりよく実践できるようになります。そうした日々の実践の積み重ねが能力となり、新たな戦略を可能とし、また習慣化した新たな関わり方がやがて人格を形成します。
アダム自身も、自らの習慣を振り返り、新しい習慣を身につける努力を続けています。本書では、彼がどの習慣に苦労しているかも率直に語られています。読者の皆さんも、七つの習慣のうち「自分がすでにできているもの」「これから意識的に取り組む必要があるもの」を考えながら読み進めていただければと思います。
既存の著作における本書の位置づけ
これまで出版されたアダムの五冊の著書は、どれも職場や事業、社会をよりよくしたいと願う人たち、つまり、市場や社会といったシステム内側のプレイヤーと、システムの外側から伴走支援するファシリテーターのために書かれています。一作目の『それでも、対話を始めよう』(旧『手ごわい問題は、対話で解決する』)は、ダウンローディング、ディベートからダイアログ、プレゼンシングを導く対話のファシリテーションについて、三作目の『社会変革のシナリオ・プランニング』は不確実な未来に備えながら可能性の枠組みを広げる変容型シナリオ・プラニングについて、そして五作目の『共に変容するファシリテーション』はトップダウン的な垂直型とボトムアップ的な水平型ファシリテーションを統合するアプローチについて、彼の理論と実践の体系をまとめた著書です。これらはシステム内外でファシリテーターの役割を担う人にとって有用な、ファシリテーションの指南書としての位置づけられる書籍です。
一方で、二作目『未来を変えるためにほんとうに必要なこと』は、ファシリテーターが「再統合の衝動(愛)」を重視して全体の利益と調和を促そうとするあまりに、個々の当事者の「自己実現の衝動(力)」や、当事者の利害をないがしろにしがちなリスクを踏まえて、愛と力のバランスを提唱しました。四作目の『敵とのコラボレーション』では「技術的な問題」(ハイフェッツ)や「明確・煩雑」な課題(コリガン)に適用される、従来型コラボレーションの三つの前提(「全体の利益と調和」、「問題と解決策への合意」、「一人のリーダーが他者の行動を変える」)について疑問を投げかけ、新しい前提に基づく「ストレッチ・コラボレーション」を関係者たちに求めるものでした。これらの書籍は、主眼をシステムの内側で日々変容に関わるプレイヤーに置く一方で、システムの外側から支援するファシリテーターも認識すべき協働の発展した姿を提示します。いわば、システム変容に関わる組織内部と外部、当事者とファシリテーターすべてを対象にした、新しいリーダーシップを指南するものとして位置づけられ六作目となる本書は、二作目、四作目の延長上に生まれた、システムの中で変容を求めるリーダーと彼らに伴走するファシリテーターに向けて書かれた、より効果的な協働を基軸にするリーダーシップの指南書と言えるのではないでしょうか。その意義は、システム変容を起こすプロセスやメカニズムを念頭に、センゲらの提唱する「システム・リーダーシップ」、すなわちシステム変容のための協働を育む集合的なリーダーシップの具体的な実践に通じます。システム・リーダーシップの実践の要諦は、外側に表れる行動様式や他者との関わり方(アウター)と、内側で起こる気づきやあり方(インナー)の両面を循環させる実践を指向します。本書で提示される「根源からの関わり」は、まさにこのシステム・リーダーシップを体現する慣行そのものであり、センゲらもU理論と並び現場で構築された重要な実践体系として注目しています。日々の行動や習慣を通じて他者と深くつながり、内面の自己を磨きながら外のシステムに働きかける―その営みが、システムを持続的に変容させる力となります。
システム横断で対話し、システム的に考える
アダムの以前の著書と対比したとき、HABIT 7「忍耐強く続け、休息する」については今回が初出で、これは気候変動問題に取り組むシステムリーダーたちへのインタビューをまとめた冊子『Radical Collaboration』に掲載されたものです。HABIT 3「見えないことに目を向ける」、HABIT 5「進むべき道を模索する」、HABIT 6「異なる他者と協働する」はこれまでの著作の主張にほぼ重なりますが、リーダーシップを体現する慣行としてよりわかりやすく記述されています。そして、HABIT 1「責任を引き受けて行動する」、HABIT 2「三つの次元で(他者と)関わる」、HABIT 4「裂け目に働きかける」は、部分的にこれまでの著作でも言及されていましたが、今回新しい視点が埋めこまれて大きく進化した印象があります。
本書の最大の特徴の一つは、従来からのアダムの対話・協働の体系に、ドネラ・メドウズ、フランシス・ウェストリーらによる複雑システムの理論と実践を掛け合わせていることと言えるでしょう。フランシスについてはHABIT 4で詳しく述べられているので、この解説ではドネラ・メドウズについて補足します。
ドネラ・メドウズは、一九七二年ローマクラブより発表された『成長の限界』の主著者であり、システムダイナミクスを駆使して地球における人口、経済、環境の相互作用に関するグローバルモデルおよびさまざまなシナリオのシミュレーションを示し、サステナビリティの概念を最初に打ち出したことで知られています。また、「氷山モデル」や「システム原型」を用いて、システム思考をわかりやすく市民に伝えようとした功績でも知られており、アダム・カヘンもワークショップでは氷山モデルをしばしば活用しています。ドネラ・メドウズの「システムに介入する12の場所」の論文は、小さな力で大きく持続的な成果を生むレバレッジ・ポイントを具体的に見出す指南書として、ソーシャルイノベーションやシステムチェンジの分野で広く読まれています。HABIT 4の「裂け目に働きかける」は、まさにレバレッジ・ポイントを探る奥義を探求する実践です。
彼女はまた、食糧問題や国際協力問題などの社会経済システムの難しい課題に取り組みながら、対象となるシステムを科学的、大局的に見るだけでなく、五つのソフトスキル、すなわち「ビジョンを描く」「ネットワークを築く」「真実を語る」「学ぶ」そして「慈しむ」ことの実践を推奨します。アダム・カヘンが日々の習慣の着想に至るインスピレーションもまた、ドネラ・メドウズが与えたものだと私は考えています。ドネラ・メドウズらのシステム科学者が、事象のダイナミックな複雑性を「システム的に考える」ことへ貢献した一方で、アダム・カヘンらファシリテーターは「システム横断的に話し、共に考える」ことで、社会的な複雑性を相互に理解することを進めてきました。アダムはこれまで四つの話し方・聞き方モデルを示し、全体か部分かの対立や葛藤を扱い、両立する可能性を模索してきました。
今回、アダムが執筆過程でも最も悩み、大幅に書き直したHABIT 2において、システム思考において重視される「部分と部分の関係性」という新たな軸を打ち出すことで、両立へ向かうプロセスの具体的なイメージがより明確になりました。互いに緊張感を持って交渉する相手であると同時に、相互の信頼や理解に基づく同胞としての関係性を築くことによって、生成的な複雑性に向き合うことで現れる共創(コ・エマージェンス)の可能性を打ち出しています。ドネラ・メドウズらのシステム思考家たち、そしてアダム・カヘンらのファシリテーションの先駆者たちの実践を統合するアプローチとして、今回のアダムの新作は感慨深いものです。
つながり、主体性、正義が生成的なシステム変容をもたらす
本書のもう一つの特徴は、新しいリーダーシップ・アプローチの提示です。いわゆるトップダウン的な専門家・マネジメント型などのアプローチでもなく、またボトムアップ的なサーバント・ファシリテーター型などでもない、いわば第三のアプローチであり、それはシステム・リーダーシップに通底するものです。
以前の書籍では、「愛」と「力」の概念を用いていました。どちらも日常的に使われる言葉であり、誤解も生まれやすいですが、アダムは神学者パウル・ティリッヒの定義に基づき、「力」は自己実現を求める衝動(主体性)であり、「愛」は分かたれたものが再統合を求める衝動(つながり)と定義して彼の理論を構築しました。キング牧師の言葉、「愛なき力は無謀で乱用をきたすものであり、力なき愛は感傷的で実行力に乏しい」を引用し、力と愛が互いを否定するのではなく、自らの弱い衝動を強めることでバランスをとるのだと主張しています。
しかし、バランスをとって循環するのでは、社会のシステム変容に不十分ではないかとの実践者たちからの問いに向き合い、アダムは第五作の『共に変容するファシリテーション』において、ティリッヒの説いた第三軸である「正義(justice)」の概念を加えました。つまり、力と愛の両極間の循環が不正義に向かうのは退行的であり、正義、つまり「不公正を減らしエクイティを高める」方向に向かうことが、循環しながらも前進していくことを示す軸であるとしたのです。
2023年、アダムが来日して講演を行った際に、日本人聴衆の多くが「正義」という言葉に反応しました。「正義を振りかざす」という表現がありますが、日本では強く大きな権力者や勝者が正義の何たるかを決めることや、あるいは活動家がむやみに正義を訴えることの悪印象が拭いきれなかったのかと推察します。本書の翻訳においても、justice をいかに訳すか大いに悩みました。
ソーシャルイノベーションやビジネスの新しいチャレンジにおいて、justice という言葉は、「法的正義」や「応報的正義」に限られるものではなく、「社会的正義」「環境正義」「経済的正義」「地球規模の正義」へと、その課題分野が広がっています。本書では、「正義」という概念を日本の一般的な感覚ではなく、国際的でより開かれた進歩的な文脈で捉え直すために、あえて「正義」という訳語を採用することとしました。ティリッヒは、「正義は、愛が社会関係の中で実現される形態である」と定義します。つまり彼の言う「正義」は、権利・機会・社会制度の公平性を確保する「社会的正義」を越えて、そして被害者やコミュニティへの損害を回復し、関係性を修復する「修復的正義」を包含します。
本書で紹介されるリーダーたちが示すのは、ただ全体最適や調和を求めて個をないがしろにしたり(力なき愛)、ただ特定個人やグループの利益を優先して機能しないシステムを放置したり(愛なき力)、ただ倫理的に正義を他者に強要したりするリーダーシップではありません。協働を効果的にするリーダーシップの実践では、しばしばシステム的に存在する不正義、不公正、格差という多くの人が気づいている裂け目に向き合い、根源からの関わりを通じて多くの人の共感、参画、主体性の力を集め、そしてつながり、調和、共有ビジョンや新しい価値観の共有をファシリテートするような三軸上のダイナミックな動きを感じます。「つながり(愛)」「主体性(力)」「正義」が、相互補完的に高まるリーダーシップ実践が、生成的なシステム変容の条件を整えているのです。
日本における実践
おりしも、今ほど日本社会でシステム変容の実践が求められているときはないでしょう。ビジネスにおけるイノベーションにせよ、社会課題に取り組む上でのソーシャルイノベーションにせよ、個別の組織やプロジェクトの取り組みによってある程度の成果はあっても、要素それぞれの技術や改善には限界があり、組み合わせやシナジー、抜本的・連鎖的な変化までには及んでいません。むしろ、個々のプレイヤー間のリソース獲得競争や二項対立、トレードオフ、膠着が支配的になっている向きが強いように見受けられます。システム変容、システム投資、システミックデザイン、統合アプローチといったキーワードが注目を集め、さまざまなシステム変容者がその実践方法を探っています。世界にあるシステム事例はそれぞれ独特で、特定の施策や戦略をベストプラクティスとして、スケールアップ的な発想で採り入れるのは注意が必要です。しかし、スケールアウトの観点で見るならば、アダムの示す日々の実践は、システム内のプレイヤーたちが主体的につながり合い、正義に向けて前進していくための基本習慣、そしてそれらを根源的にするための自己認識やあり方を指南してくれるものです。
読み進める際には、ぜひ自分の足元のシステムを一つ思い浮かべてみてください。学校教育、介護現場、サプライチェーン、NPOの資金循環、気候変動への市民アクション―どのようなシステムでも構いません。各章末に用意された演習に対し、ノートを開いて内省のためのメモをとり、その後数ヵ月、数年にわたる自分自身のラーニング・ジャーニーを振り返ることをお勧めします。ストレッチも習慣によって可動域が伸びるように、行動の積み重ねによって自身の境界が広がり、システム変容に向けてより効果的な行動がとれるようになることでしょう。
アダムは日本の文化をこよなく愛し、執筆活動の折りに触れ日本を訪れます。本書の企画・執筆も、アダムが来日して京都の小倉山を散策した際に交わした会話がきっかけとなりました。ファシリテーターやチェンジ・エージェントにとっての共通の関心事として、システム変容あるいはシステムチェンジについて対話する中で浮かび上がってきたのは、「東洋思想の薫陶を受けたシステム思考の先人たちの智慧や体系を理解・実践するためのカギとなるのは、彼らの行う日々の習慣ではないか?」という着想です。アダムは宿へ戻るとすぐに企画書を書きあげて出版社に送り、この著作のプロジェクトが始まることとなりました。本書の着想の一助になれたことを光栄に思うと同時に、異なる領域、文化からも常に学び、進化していくアダムの職人的な姿勢と実践には、敬意と驚きを抱きます。彼こそ学び続ける実践家のロールモデルでしょう。
本書の実現に尽力くださった英治出版の桑江リリーさん、高野達成さん、下田理さんに感謝申しあげます。翻訳にあたっては、佐藤千鶴子さん、江上由希子さん、三好敦子さんのチームに支援いただきました。そして日本語版訳出の機会をくださり、いつもながら惜しみないサポートをいただいたアダム・カヘン氏に深く感謝いたします。本書が、読者の皆さんの暮らし、職場、そして社会における人々がより根源から関わる一助となって、私たちの心から望む未来を阻害する行き詰まりの根本原因に取り組み、不公正なく、主体性とつながりの調和がとれた組織や地域が日本各地に広がることを願っています。
2025年7月
小田理一郎
関連する記事
- アダム・カヘン新著『Everyday Habits for Transforming Systems』の紹介
- 世界のチェンジ・エージェント(2)アダム・カヘン氏(前編)
- 世界のチェンジ・エージェント(2)アダム・カヘン氏(後編)
- アダム・カヘン氏講演録「共に変容するファシリテーション」(1)
- アダム・カヘン氏講演録「共に変容するファシリテーション」(2)
- アダム・カヘン氏講演録「共に変容するファシリテーション」(3)
- アダム・カヘン氏講演録「社会システムに変容をもたらすためのラディカル・コラボレーション: 愛・⼒・公義に取り組み、「共に」「前へ」「進む」」(前編)
- アダム・カヘン氏講演録「社会システムに変容をもたらすためのラディカル・コラボレーション: 愛・⼒・公義に取り組み、「共に」「前へ」「進む」」(後編)
関連する書籍
- アダム・カヘン著『共に変容するファシリテーション』(英治出版)
- アダム・カヘン著『それでも、対話をはじめよう』(英治出版)
- アダム・カヘン著『敵とのコラボレーション』(英治出版)
- アダム・カヘン著『社会変革のシナリオ・プランニング』(英治出版)